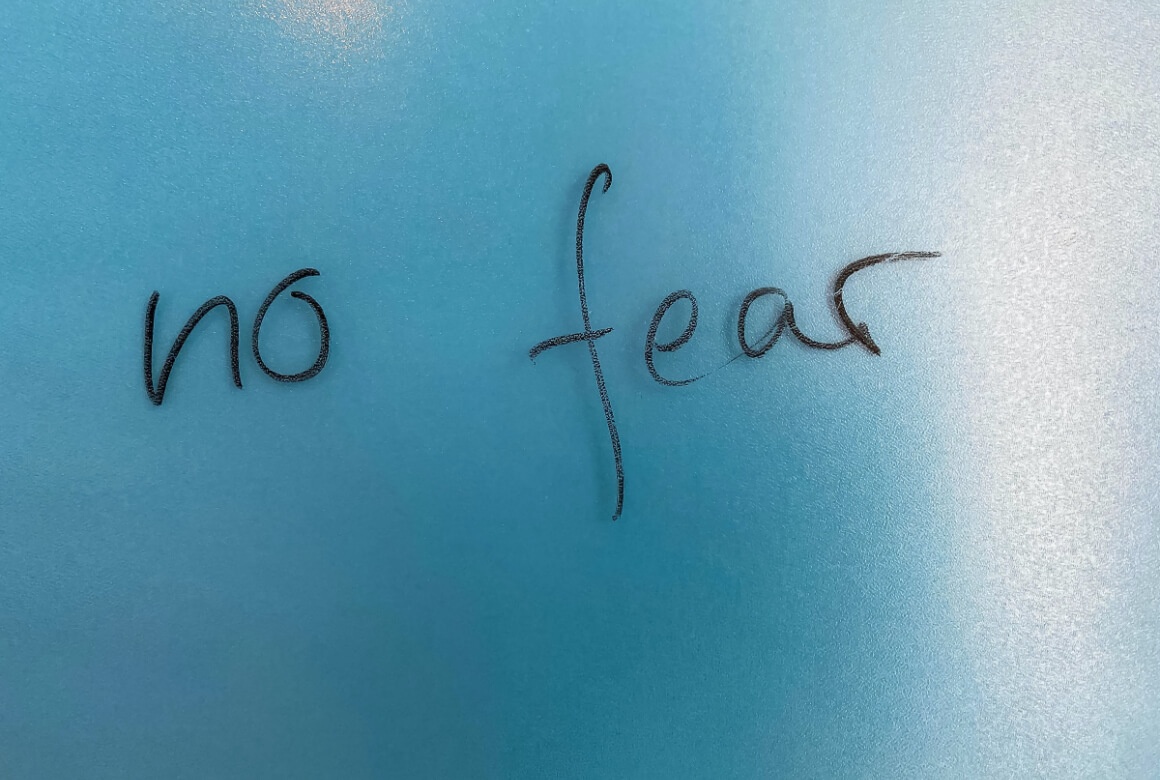Foresight
Jun. 25, 2018

カウンターカルチャーと野生。地球市民としての共感とは?
ウェルビーイングに資する適正なテクノロジーとは
[松島倫明]『WIRED』日本版 編集長
2018年6月から『WIRED(ワイアード)』日本版の編集長を務める松島倫明氏。「『WIRED』は学生時代から愛読していましたし、テクノロジーの進展と人間の文化・ライフスタイルの相互作用を先進的に提示していこうとする姿勢は、僕自身のこれまでの仕事とも重なるところが大きい」という。
前職は出版社で翻訳書の版権取得・編集を担当していた。特にテクノロジーの進展や、技術革新が進んだ時代の人間のあり方を探る本を多く手掛け、米国版『WIRED』の創刊や編集に携わっていたケヴィン・ケリー氏やクリス・アンダーソン氏* の本の日本語版も世に送り出してきた。
「一緒に歩んできた感覚があるので、『WIRED』への参加は自分の中では大転身というわけでなく、むしろどこか必然性さえ感じるほど」。これまで取り組んできたことと通底するテーマを、新しいスタイルで世に問うていきたいと抱負を語る松島氏に、まずは翻訳書の編集にかける思いやこれまでのキャリアにつながる思索の道のりについて聞いた。
テクノロジーが起こすパラダイムチェンジをとらえたい
僕が関心を寄せている事柄を整理すると、大きく2つのテーマに分けられます。
1つは「デジタルテクノロジー」です。編集した翻訳書でいえば、『〈インターネット〉の次に来るもの――未来を決める12の法則』(ケヴィン・ケリー、以下いずれもNHK出版)**、『FREE――〈無料〉からお金を生みだす新戦略』(クリス・アンダーソン)、『SHARE――〈共有〉からビジネスを生みだす新戦略』(レイチェル・ボッツマン、ルー・ロジャース)、『ポスト・ヒューマン誕生――コンピュータが人類の知性を超えるとき』(レイ・カーツワイル)などが挙げられます。
僕自身はテクノロジーが特別好きなわけでも、ましてやテッキーというわけでもないんですけど、テクノロジーがどうやって社会や人々の意識を変えていくかということには興味があります。個別のテクノロジーや企業の浮き沈みのような表層的な話ではなく、その裏側にある大きな方向性を提示して、パラダイムチェンジをとらえたい。
インターネットが普及して、無料のメディアも増えたいま、人々がお金を払ってまで読みたいものといえば、ある種のインサイト(洞察)が含まれたものではないかと思うんですね。読み捨てで終わる情報ではなく、未来の指針や人類の大きな方向性が感じ取れるようなもの。そういう書物は200~300ページの紙幅を費やすことで強度が生じると思うし、強度があればこそ人の心に残っていくのではないかと思います。
身体を起点に野生の感覚を取り戻す
もう1つ、追いかけているテーマとしては「フィジカル」、すなわち身体性や野生があります。手掛けた翻訳書のタイトルでいえば、『BORN TO RUN 走るために生まれた』(クリストファー・マクドゥーガル)や『GO WILD 野生の体を取り戻せ!』(ジョン J.レイティ、リチャード・マニング)などが該当します。
このテーマは自分の中ではテクノロジーと両輪です。現代のようにあらゆるものがデジタルに置き換わっていくとき、人間はデジタル化によってそもそも何をしたかったのか、あるいは人間の幸せって何だっけということを考えさせられることがしばしばあります。そのときに示唆をもたらしてくれるのが人間の体だと思うんです。
人類が誕生しておよそ20万年経ちますが、これだけの長きに渡っても何が快適で、何が不快かといった生物としての根幹、野生の部分は変わっていません。そう考えると、デジタル時代の人間の充足感、幸福感、ウェルビーイングを探るにあたって、自分自身の身体が重要なインターフェースになるはず。
有酸素運動をすれば充足感が高まることは脳科学で明らかになっていますし、スキンシップによって幸せホルモンとも呼ばれるオキシトシンが分泌されることも知られています。つまり、身体に根差したアクティビティこそが、幸福度やウェルビーイングと直接つながっているわけです。
最近は特に知的生産性を追求しようとか、効率よく発想力を高めようといったことが盛んにいわれていますけど、そういう取り組みも人間の心と身体のインタラクションがうまく機能してこそ成果が得られるのではないでしょうか。
テクノロジーが発展すればするほど、そもそも人間にとっての幸福や満足とは何か、という問いの重要性はさらに増していくと思うし、そこで自分の身体を起点にして、野生の感覚を取り戻していくことには大きな意味があると思います。
テクノロジーの意義を問い直した『Whole Earth Catalogue』
僕のこうした考え方の原点には、1968年にアメリカで創刊された、カウンターカルチャーのバイブルのような雑誌『Whole Earth Catalogue(ホールアースカタログ)』があります。
1960年代といえば、高度資本主義が世界を席捲し、特にアメリカや先進諸国で大量生産、大量消費、大量廃棄のサイクルが回り始めた時期です。中流階級が増え、学生もマス教育を受けて資本主義の歯車として社会に巣立つことが求められるようになりました。
国際情勢では冷戦があり、テクノロジーの究極の形態ともいうべき原子爆弾によって人々は核の恐怖を味わい、ベトナム戦争などで兵器が使われ、多くの人命が失われました。また、レイチェル・カーソンが『沈黙の春』(1962年)を刊行するなど、環境問題が前景に現れてきた時代でもありました。
いってみればテクノロジーが僕ら一人ひとりの手をすり抜けて、あまりにも大きくなって社会をも凌駕してしまうようなものになった。進歩と未来を約束してくれるテクノロジーが、一方で戦争や環境破壊によって人々の暮らしや自然を脅かしている。60年代にそのことに異議を唱え、テクノロジーと人間の関係を問い直す動きの一端が『Whole Earth Catalogue』だったわけです。
この雑誌はタイトル通り、地球全体を起点にして、もう一度思考や生活様式、生き方を組み立て直そうよと呼びかけるものでした。意識を自分たちの身の回りだけでなく、地球規模にまで拡張して、平和なり環境なり人間らしい生き方というものを達成させるため、「適正なテクノロジー」*** を取り戻すことが当時の1つのテーマだったのです。
メインストリームの対抗軸としてカウンター的な思考が重要
そういう60年代のカウンターカルチャーの精神はアメリカ西海岸にはいまも残っていて、その上に『WIRED』や現在のデジタルテクノロジーの企業が生まれているわけです。例えばフェイスブックが「世界中の人と人を結びつけることで平和をもたらす」とか、グーグルが「検索エンジンを通じて誰もが世界中の情報にアクセスできるようにする」といったミッションを掲げるのは、まさにホールアース的な思想といえるでしょう。
AIやロボットが進化すると人々の仕事が奪われるとか、あるいはテクノロジーが人間を凌駕するレベルにまで育っていくという恐怖感が人々の間にあるけれども、脅威化するテクノロジーやそれを使役するシステムをメインストリームと位置付けるならば、その対抗軸としてカウンター的な思考がいまこそ重要になるのではないでしょうか。
SNSについても、人々を結びつけたり、クラウドファンディングで資金集めを容易にしたりといったポジティブな効果を生んだ一方で、フェイスブックを見続けると人の幸福度は下がるという研究結果も出ています。自動車が普及して社会が発展した一方で交通事故が増えたのと同じで、デジタルテクノロジーには良い面も悪い面もある。それが脅威だからといって原始的な生活に戻ればいいということではないし、いまさらそんなこともできません。
ならば、自分たちが本当に望む適正なテクノロジーは何かを考えて、選び取っていくしかない。世の中にあふれるテクノロジーの中から良いものを見極めることは難しいかもしれないけれども、僕はあえて楽観的に構えた上で、適正なテクノロジーについて情報を発信していくことが大切だと思うんです。
フェイスブックもグーグルもアマゾンも、いまや社会のインフラであり、新たな独占企業になっています。それをどうやって自分たちが制御するか、あるいはデジタル空間のあちこちに存在する個人データをいかにコントロールするか。EUはこの問題の整備に着手していて、今後この流れは世界的に波及していくと思われますが、喫緊の課題として誰もが意識して向き合っていく必要があるでしょう。
 『WIRED』は米国で1993年にもともと雑誌として創刊。テクノロジーによって人間の生活や社会、文化がどのように変化するか、その未来像を提起する。雑誌およびウェブ版が米国、イギリス、イタリア、ドイツ、日本でそれぞれ発行されているほか、台湾では中国語版ウェブサイトが開設されている。
『WIRED』は米国で1993年にもともと雑誌として創刊。テクノロジーによって人間の生活や社会、文化がどのように変化するか、その未来像を提起する。雑誌およびウェブ版が米国、イギリス、イタリア、ドイツ、日本でそれぞれ発行されているほか、台湾では中国語版ウェブサイトが開設されている。
日本語版の雑誌は1994年に創刊。一時休刊を経て、2011年6月より再刊。
https://wired.jp/
* ケヴィン・ケリー氏は『WIRED』の創刊編集長で、クリス・アンダーソン氏は元編集長。
**ワークサイトでは、ケヴィン・ケリー氏が登壇した同書の出版記念講演会を取材、レポートしている。記事はこちら。
前編「これからのビジネスの方程式は『X+AI』」
後編「人間のミッションは答えのない問いを探索すること」
 松島氏が編集した本は「Booklog」上にまとめられている。
松島氏が編集した本は「Booklog」上にまとめられている。
https://booklog.jp/users/matsushima-m
*** 適正なテクノロジー
大組織のためでなく、個人にとって役立つテクノロジー。経済学者のエルンスト・シューマッハらが提唱したコンセプトで、『Whole Earth Catalogue』でも大きく取り上げられた。

SNSで千人規模の友人がいるこの状況は
人類史上例のない社会実験である
ホールアースという文脈でさらにいうならば、「共感力」(compassion)も大きなキーワードであると思います。
先ほどのSNSの話じゃないですけど、テクノロジーによって僕らは国や地域を超えて人々と交流できるようになりました。理論的には地球の総人口76億人とコミュニケーションすることも可能でしょう。でも一方で共感を伴うコミュニケーションができるのは、せいぜい150~160人程度という説があります。これをダンバー数といって、いわば昔の部族社会のイメージですね。
いまの状況は非常に面白い社会実験だと思います。フェイスブックで1,000人、2,000人といった規模の人と友だちになっているこの状況は、人類の限界を超えたかりそめのものなのか、それともテクノロジーによって人間の共感の届く範囲が実際に広がっているのか。
僕自身は広がっていると思うんです。『限界費用ゼロ社会――〈モノのインターネット〉と共有型経済の台頭』や『スマート・ジャパンへの提言』の著者である未来学者のジェレミー・リフキンは、人類の進化はいかに共感の幅を広げていけるかということとパラレルだと指摘しています。
原始的な部族社会であれば、コミュニケーションの単位はまず家族や親戚で、社会の拡大と共にそれが部族になり、さらに村や地域へと広がっていく。その過程で別の共同体、別の民族を敵と見なす風潮も生み出され、やがて都市ができて国家が成立しても、常に内部に味方が、外部に敵が作られていくわけです。
地球全体を自分たちの生態圏として共感の幅を広げられるか
テクノロジーによってコミュニケーションの範囲が劇的に拡大したいま、国家から地球へと共感の範囲も広げられるかどうか。これが現代の僕らに突き付けられている課題ではないかと思います。
例えば、動物の権利を尊重しようとヴィーガニズム**** を実践する人が欧米では増えています。犬や猫と同じように、牛や豚、鶏にも感情があるのだから屠殺すべきでないと、共感の範囲を広げているわけです。同じように、一度壊した森林環境や生態系は戻すのに大変な時間がかかることもわかっているし、わかったときに共感の幅を広げて倫理的な行動を起こしていくかどうかは、僕ら自身の判断に委ねられています。
そして、テクノロジーはコミュニケーションの範囲だけでなく、共感の範囲を広げるための手段にもなり得るでしょう。鳴き声やしぐさから動物の感情を察知する技術もありますし、IoTで人間だけでなくあらゆるものが今後結びついていけば、地球全体を1つの生命体と見なすような動きがもたらされるかもしれません。
人類だけでなく、動物や植物といった自然環境も含めて、地球全体を自分たちの生態圏として、そこに共感の幅を広げられるかというのが、テクノロジー的なチャレンジでもあるのです。
自然に打ちのめされることで他者への共感が養われる
ここでカギになるのがフィジカルです。共感や思いやり、利他的な精神というものは頭で考えて備わるものではなくて、体を動かすことによって生まれます。走ることもマインドフルネスも、あるいは先ほどいったスキンシップも、身体を通じて外部とつながる感覚を得るということ。しかもそれを仲間と一緒に行うことで、トライブ(種族)意識のようなものも生まれて、利他的な共感力はいっそう強くなるでしょうし、それは1つのウェルビーイングでもあると思います。
例えば僕は山野を走るトレイルランニングが好きなんですけど、これは有酸素運動になるし、自然の中で心身を活性化するといった利点があります。ただ、自然界は厳しい淘汰の世界でもあり、生と死は隣り合わせです。トレイルを駆けるという行為は、岩場で足を取られ、天候に翻弄され、急峻な登りに心身が打ち砕かれる経験でもあるわけです。そうやって自然に打ちのめされ畏怖の念を抱くことで人は謙虚になれるし、そこから他者への優しさや共感が生まれてくると思うんです。
そんなふうにフィジカルに根差したウェルビーイングの追求と、全地球レベルでの共感の拡大が、ほぼ同時に進んでいるのがいまの時代の構図ではないでしょうか。
そこで、どうやってテクノロジーを使っていくか。テクノロジーに振り回されるのではなく、自分たちが目指すものを実現するためにいかにテクノロジーを役立てていくか。例えばテレワークで緑豊かな場所で働くとか、地域でコミュニティを作るとか、そういう使い方もあり得るでしょう。人間の生活とテクノロジーのどちらを上位に位置づけるかの判断がしっかりしていれば、適正なテクノロジーの実現は決して難しいことではないと思います。
WEB限定コンテンツ
(2018.4.24 渋谷区にて取材)
text: Yoshie Kaneko
photo: Chihiro Ichinose
**** ヴィーガニズム
絶対菜食主義。

松島倫明(まつしま・みちあき)
『WIRED』日本版 編集長。1972年東京生まれ。一橋大学社会学部卒業後、1995年株式会社NHK出版に入社。村上龍氏のメールマガジンJMMやその単行本化などを手がけたのち、2004年からは翻訳書の版権取得・編集・プロモーションなどに従事。『FREE』『SHARE』『ZERO to ONE』『MAKERS 21世紀の産業革命が始まる』『〈インターネット〉の次に来るもの』『BORN TO RUN』など、数々の話題書を生み出した。2018年6月より現職。


![働くしくみと空間をつくるマガジン[ワークサイト]](/images/common/ttl-catch_copy-002.png)