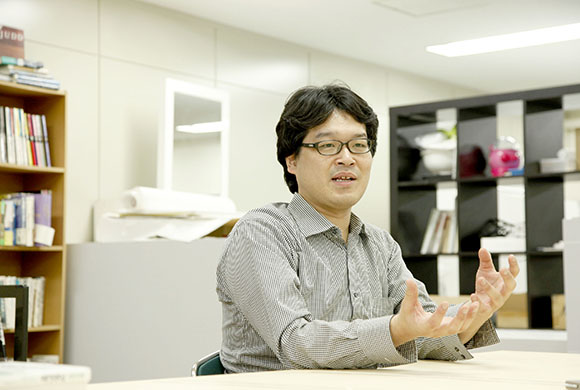Management
Apr. 6, 2020

週15分~1時間の「超短時間雇用」で、障害者の就労拡大へ
就労先を多様化してワーカーシェアリングを実現
[近藤武夫]東京大学 先端科学技術研究センター 人間支援工学分野 准教授
障害の有無に関わらず、みんながともに学び、働くことのできる社会システムの構築に向けて研究に取り組んできました。その一環として生まれたのが、企業での柔軟な働き方を生み出す雇用モデル「超短時間雇用モデル」です。週あたり15分や1時間といったごく短い時間からの雇用を実現することからこのように呼んでいます。
雇用する側は、例えば「商品情報の英訳」「胃カメラの洗浄」といった具合に、依頼する業務を具体的に定義します。そして、その作業を請け負うことができる障害者が、その仕事だけを引き受けるのです。ジョブ単位で仕事を依頼するので、短時間でも雇用が成り立つわけです。
企業としては人手不足を解消できる、業務に特化した助っ人が得られるといった利点がありますし、ワーカー側としても就労のハードルを下げられる、他の業務まで派生する心配がないといったメリットがあります。
日本型雇用の「長時間労働」と「職務定義の不在」が障壁に
いま、日本には障害を持つ人が963.5万人います。そのうち身体障害者は436万人、知的障害者は108.2万人、精神障害者は419.3万人* です。民間企業が雇用している障害者は56.6万** に過ぎず、たとえ働きたいと障害者が考えていても、十分にその機会を得られない現状があります。在宅生活や施設と自宅を往復する毎日を余儀なくされている人もいます。
障害者の就労を阻む要素として多くのものが挙げられますが、日本型雇用の特徴である「長時間労働」と「職務定義の不在」に私は着目しています。
一般的に健常者と呼ばれる人の労働時間は週40時間で、しかも年間を通じて働くことが前提とされています。これに準じた形で障害者雇⽤でも通年で週20~30時間働くことが求められます。これだけ働くことが難しい障害者はたくさんいて、無理して長く働くことで体調を崩す人もいますし、そもそも働くことをあきらめてしまう人も少なくありません。長時間、長期に渡って安定して働けない⼈は雇⽤対象から排除されてしまうわけです。
もう1つ、職務定義がないことも日本型雇用の特徴です。要は採用時に何をするかが決まっていないんですね。配置転換で仕事内容がガラッと変わるので、雇用主である企業の求めに応じて、臨機応変に何でもできる⼈が労働者として期待されることになる。また、職務と給与が対応しておらず、年功序列で主任、係長、課長と管理職として昇進していくうちに、給与も上がっていくという雇用慣行があります。
企業が新卒採用で最も重視する要素はコミュニケーション能力の高さと言われます。これには異動先で空気を読んで対応できることが求められている、また誰もが管理職になることが期待されているといった背景があります。ただその代わり、1つの企業で長期間に渡って雇用され、生活保障がなされてきたという、労働者にとって有利な側面があるのも事実です。
職務定義を作ることに企業が慣れていないと、特定の部署で必要とされている職務と、そのためのスキルの構造化ができないから、労働者に求めるべき力が定義できない。従って特定分野ではできることがあっても何か他に極端にできないことがある⼈、ジェネラリストになることが難しい人は採用されにくく、労働市場からつまはじきにされてしまうのです。

東京大学 先端科学技術研究センターは、学際性・流動性・国際性・公開性という4つの基本理念に基づき、文系と理系の垣根を越えた研究活動を行っている。
https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/index.html
近藤氏が携わる主なプロジェクト。
・超短時間雇用を含めた、インクルーシブかつ多様性を歓迎する配慮ある働き方を研究する「IDEAプロジェクト」。
http://ideap.tokyo/
・障害と高等教育に関するプラットフォーム形成事業「PHED」。
http://phed.jp
・音声教材のオンライン図書館プロジェクト「Access Reading」。
http://accessreading.org
・テクノロジーを活用して障害のある子どもたちの学習や進学をバックアップするための研究プロジェクト「DO-IT Japan」。
http://doit-japan.org
* 数字はいずれも「平成30年版 厚生労働白書」(厚生労働省発表)より。
** 「令和元年 障害者雇用状況の集計結果」(厚生労働省発表)
障害者の法定雇用率に隠れた排除
日本型雇用の雇用慣行が生まれたのは第二次世界大戦で、高度経済成長期にそれが固定化してきたと言われています。また、「企業が労働者の生活保障をする」という社会通念も、もともと戦前から大きな社会格差があったところに、戦争で日本全国焼け野原になって、政府によるセーフティネットが十分機能できず、企業の側が生活保障やセーフティネットの役割を果たすことが社会的に求められてきたという歴史があります。そうした歴史が根底にあって、いまでも雇用する側は労働者の生活保障をしようと考え、ならば長い時間働いてもらわねば、という理屈につながっています。
最近では、高度な専門性を持つ人に対しては高度プロフェッショナル労働制や裁量労働制の適用で、労働時間枠を撤廃する動きが広がっています。このことの背景には、賃金の効率化・圧縮を図る面があるでしょう。
しかし、いわゆる高度人材にあたらない多数派の人たちは、雇用主が善意で「労働者の生活保障をしよう」と考えると、そのために必要となる賃金を確保すべく、できるだけ長時間、可能ならフルタイムで、職場で働けるようにしよう、という発想になるのは当然です。
とはいえ、障害や病気のある人たちなど、一部の人たちには、それが難しい場合があります。生活保障することを基礎に置くと、長時間働けない人は職を得にくいことになってしまう。そうした人たちの生活保障は、働いて給与を得ることではなくて、生活保護や障害年金などの公的扶助だけに頼らざるを得なくなる。思い切り働くか、働かずに公的扶助で生きていくか、その中間がないというか、選択肢が非常に少ないのが現状です。
戦後の障害者雇用施策は、障害者も日本型雇用で働き、公的扶助に頼らずに生きていけるよう生活保障することを目指してきたと言ってもいいでしょう。民間企業に法定雇用率の目標値*** を掲げて障害者の雇用拡大を促していますが、雇用率にカウントするため、1名の障害者を雇用したと企業が報告するためには、基本的には、障害者手帳を持つ個人を、通年で週30時間以上雇用することが必要です。
事実、雇用率の成果で、障害者の一般企業での雇用は拡大してきました。この障害者雇用施策で求められる、年間を通じて週30時間働くことができる、という要件に一致しない人々は、雇用機会から排除されてきた面も否めません。既存の障害者雇用施策の中で、熱い思いで取り組んでいる方々もたくさん知っていますけれども、それだけにとどまらず、労働スタイルの柔軟性に欠ける日本型雇用という本丸に切り込んでいき、新しい働き方を生み出していくこともまた、重要でしょう。
福祉的就労の現場にある課題
一般企業での雇用というゴールを目指して、国によるさまざまな中間支援事業もなされています。しかしそこにも、法定雇用率や日本型雇用の壁が影響しています。
例えば、企業への就職を支援する就労移行支援事業所では、そもそも企業が障害者雇用率にカウントできる人材を欲しているので、長く働けない人を事業所に受け入れることに消極的になってしまう。要は排除が働いてしまうわけです。
また就労継続支援事業として、サポート付きの労働で雇用契約があり最低賃金が適用されるA型事業所や、雇用契約がなく最低賃金が適用されないB型事業所もあります。いずれも元々は地域に居場所を作って働く喜びを提供しようという目的でできたものですが、制度の変革が進む中でいつの間にか、一般企業での就労に接続するための支援の場へと位置づけがシフトしてきました。
これらの事業所では、一般的に、給与や工賃が低いことが問題にされがちです。実際に、A型の月平均給与は7万6千円ほど、B型は最低賃金が適用されないので、工賃の全国平均は1万6千円ほどです。ただそれよりも、A型やB型事業所の利用者が、一般企業での就労と隔離されていることが課題です。
それらの事業所で働くだけでなく、就労や生活のサポートを受けながら、同時に一般企業で時給の高い業務を週数時間だけ行って高い時給をもらう、ということもあってよいと考えます。インクルーシブに働ける選択肢を増やす方策となると考えますが、制度上、それはなかなか難しい。A型やB型などの、障害者だけが働く場所に行くか、他の社員と同じように働ける障害者だけが一般企業で働くか、ここでもやはり中間的な選択肢が想定されていません。
*** 障害者の法定雇用率は2020年2月現在2.2パーセント。2021年4月までに2.3パーセントに引き上げられる予定。

大学内の研究プロジェクト遂行を
障害のある人が支援
後編で詳しく話しますけど、僕は元々障害のある子どもの学びをサポートする研究を手掛けていました。どの子もそれぞれに優れた部分があり、特定の分野で高いパフォーマンスを発揮する様子を目の当たりにして、みんなが社会で活躍できるように多様な働き方を作らないといけないと考えるようになったんです。
そこで、まずは障害を持つ人たちに僕の研究室で仕事をしてもらったんです。研究室のプロジェクトには、教育コンテンツを制作する業務など、多彩な業務があります。その業務ごとの職務定義を細かく見ていくと、特定の職務の遂行で本質的な部分をはっきり定義さえできれば、そこを遂行することができる人を雇用できるようになります。もちろん、あれもこれもとできることを求めないことは必須です。
例えば研究室では、難病のため、体力的に週5〜6時間の範囲であれば働ける、という職員がいます。聡明で、指先でコンピュータの操作も行えるので、現在はある部署のコンテンツ制作の進捗管理や、他のスタッフの業務成績のモニタリングをしてもらっていて、本当に助かっています。ただ当然、雇用率にはカウントすることはできません。
「雇用率カウントのために雇おう」と考えてしまうと、その人の得意な部分が見えにくくなる。「これができるならついでにこちらも」と求めていくと、雇えなくなる人が出てくる。「ひょっとすると、雇っているうちに、今の事務業務だけじゃなくて、客先に立つことが必要になるかもしれないから」と考えてしまうと、身だしなみやコミュニケーションも労働者に求めざるを得なくなる。
まず、自分の部署で必要とされている職務と、それを遂行できるための要件を明らかにして、それができる人であれば積極的に雇用していく。スタッフだけではなく、研究室では、精神疾患や発達障害があって、週数時間だけ特定の季節であれば体調もよく働けるという人、これまでは障害者雇用の枠組みでも働いた経験がなかった人たちにも、アルバイトとして働いてもらっています。研究室としては大いに助かっていますし、役割がはっきりしていて、ごく短時間の仕事は本人にとっても負担が軽く、都合がいいことが分かってきました。
試行錯誤しながら、障害者雇用率に関係なく、さまざまな障害のある人々と実際に仕事をしていく工夫を重ねていくうちに、独自のノウハウや知見も含めて仕組み化することができてきました。それを元に、大学以外の企業や自治体に展開していったのが、超短時間雇用モデルだったというわけです。
ソフトバンクでショートタイムワーク制度を導入
障害のある子どもの学びをサポートするDO-IT事業で協働していたソフトバンクさんも、障害者の就労先の多様化が必要だと考えていたことから、超短時間雇用モデルに賛同してくれました。そこで2016年4月、週20時間未満でも障害者が働けるショートタイムワーク制度を、僕も一緒になって同社内に策定しました。
手順としてはまず、社員が忙しく困っている部署で、どのような職務を果たしてくれる人がいたら、その部署が助かるのかを明らかにすることを行います。残業の発生につながっているもの、ある社員の本務や得意ジャンルではないけれども、誰かがやらねばならないということで積み残された仕事、業務委託するほどのボリュームはないけれども毎日1~2時間割いて取り組まないといけない仕事などを明らかにするのです。
さらにそこで挙げられた仕事の手続きを、具体的な作業手続きに分解していきます。詳細な職務定義ですね。これができてから、その職務が遂行できる人に来てもらうという段取りです。
このショートタイムワーク制度を現在までにソフトバンクの約50以上の部署で実践してきましたが、ワーカー側も会社側も満足度が高く、非常にうまくいっています。
ワーカーの1人である統合失調症の男性は、週20時間働く訓練をするたびに体調を崩していたそうです。働くことはハードルが高かったけれども、ショートタイムワーク制度による就業で社会と関われることがうれしいし、障害を隠すことなく働けることもありがたいと言っていました。迎え入れた社員の方々も、忙しいときに手伝ってもらえて助かった、業務を効率化できた、気持ちに余裕が生まれた、といったポジティブな効果が得られたそうです。
この輪を他の民間企業にも広げようということで、2016年11月にはショートタイムワークアライアンスがスタートしました。2019年末の時点で130法人が参加しています。
ソフトバンクのショートタイムワークアライアンスを紹介するサイト。
https://www.softbank.jp/corp/csr/special/stwa/
自治体への実装で、地域の障害者をシームレスに雇用
企業での取り組みがうまくいったので、次の展開として自治体での実装に取り組みました。
企業だけでは発注する仕事のボリュームに限りがあります。また、定義された職務を遂行することができて、かつ通常の障害者雇用では適応できてこなかった人材がどこにいるかも、企業にはわかりません。労働者の側も、じかに企業と連絡を取るのは困難です。そこで、企業と労働者の間に、自治体や公的な就労支援センターが入ることで、障害者雇用率とは関係なく、地域にいる障害者が雇用にシームレスにつながる仕組みを作っていきました。
僕らが役所内チームに対して共同研究の形でノウハウ提供や相談支援を行い、役所内チームは就労支援センターをマネジメントします。就労支援センターが企業の職務定義のサポートや職務に適したワーカーの紹介、適応支援などを行います。就労を希望する人は、センターの窓口に行くだけで超短時間労働への取っ掛かりができる。地域が一体となることで働く場の選択肢が広がるわけです。

地域での実装はまず、2016年に川崎市で始まりました。2019年の時点では55の企業・団体に、のべ58人が就労を果たしています。このうち48人は週10時間未満からの就労スタートでした。
その後、神戸市、渋谷区からも声がかかって、少しずつ超短時間雇用制度が拡大しています。地域で仕組み化できれば誰でも安心して働けるようになります。1社に依存して働くのではなく、A社でもB社でも、特定の職務でその人の強みを活かして働くというように、地域全体でその人を雇用することができます。ワークシェアリングならぬ、ワーカーシェアリングですね。そうしたことも可能としています。
他にも、1つの会社のみで長く働くだけではなく、たとえそこでうまくいかなかったとしても、他の会社にも地域の支えで流動できるという利点もあります。
地域の企業で雇用実績をまとめる積算型雇用率
将来的には、地域の企業で雇用実績をまとめる積算型雇用率という考え方も実装できたらと思っています。
現状の障害者雇用率は1人を週30時間雇うことで初めて1カウントとなります。私たちの超短時間雇用の取り組みでは、大きな企業であれば多くの部署で少しずつ超短時間雇用を行って、全部の時間数をまとめて30時間を超えれば1カウントと考えたり、ごく少人数を超短時間で雇用している小さな企業でも、自治体内の企業での雇用時間数をまとめて30時間になったら1カウントと考えるということを行っています。
独自の制度なので助成金には結びつかないけれども、一般企業で、既存の障害者雇用では働くことが難しい人の雇用に取り組んでくれている企業はもちろん、自治体単位で見ることで、障害者の雇用参加に貢献している中小規模の企業を可視化することもできます。労働者だけでなく、企業や自治体にもメリットの得られる仕組みができれば、超短時間雇用のさらなる促進につながるはずです。
(近藤氏提供の図版を元に作成)
NHK教育テレビ「ハートネットTV」で超短時間雇用が特集された(2018年10月1日、2019年2月4日放送)。この中で神戸の事例や企業の採用の様子などが紹介されている。
https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/117/
https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/177/

超短時間雇用の実践は“まちづくり”でもある
超短時間雇用は困窮者支援とも密接に関係しています。2015年に生活困窮者自立支援法が制定され、全国的にさまざまな支援がされていますが、担当者いわく障害認定のない障害者の支援というケースが多いそうです。コミュニケーションが難しい、持病があって長時間働けない、特定のことはできるけれども、それ以外のことでどうしてもできないことがあるといった人たちが対象になるということですね。困窮者支援の取り組みは、いわば障害と貧困の汽水域なんだと思います。
そういう人は生活保護だけしかセーフティネットがない場合もあります。障害者の雇用促進施策は戦後すぐから長い歴史を持っていて、中間的な支援が困窮やその他と比べて分厚いという長所があります。障害認定されていない人も含めて、就労を希望する全ての人を雇用につなぐことが重要ですし、自治体で実践している超短時間雇用モデルの取り組みで働く人には、障害者手帳や医学的診断がないケースもあります。実際、川崎でも神戸でも、困窮者支援の担当者からも候補者が紹介されてきます。
そう考えると、地域に働ける場所を増やす超短時間雇用は、ある種の“まちづくり”でもあるわけです。神戸では商店街で超短時間雇用を進めていて、例えば老舗の料理屋さんで精神疾患のある人が穴子を焼いたり、お米を炊いたりしています。精神発達障害で家からほとんど出たことがなかった人が、喫茶店の家具の補修で週1時間仕事をしているケースもあります。
できることをできる人がやって、雇用する側は忙しいときに手を差し伸べてもらい、働く側は就労の場や社会参加の機会を得る。お互いに助け合う場がもっとたくさん出てきたら、世の中はもっと豊かに、面白くなっていくと思います。
(近藤氏提供の図版を元に作成)
WEB限定コンテンツ
(2020.1.14 目黒区の東京大学 先端科学技術研究センターにて取材)
text: Yoshie Kaneko
photo: Kazuhiro Shiraishi

近藤武夫(こんどう・たけお)
1976年生まれ。東京大学 先端科学技術研究センター 人間支援工学分野 准教授。広島大学大学院教育学研究科などをへて現職。専門はインクルーシブな教育や雇用に関する研究。主な著書に『学校でのICT利用による読み書き支援――合理的配慮のための具体的な実践』(編著、金子書房)、監修を手掛けた本に『発達障害の子を育てる本 スマホ・タブレット活用編』(講談社)など。


![働くしくみと空間をつくるマガジン[ワークサイト]](/images/common/ttl-catch_copy-002.png)