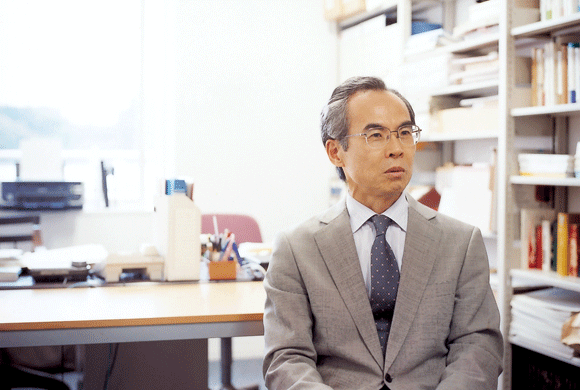Foresight
Apr. 12, 2021

「働きにくさ」と「産みにくさ」はつながっている
大企業型の働き方を象徴する3つの無限定性
[筒井淳也]立命館大学産業社会学部 教授
仕事と家族のあり方は、時代とともに大きく変化してきました。
日本でも海外でも、近代以前は仕事といえば農業、モノづくり、商いなどの家業、今でいう自営業が主流でした。家長が社長のような役割になっていることが多く、そのほとんどは夫/父親で、家でも仕事場でも年長の男性の指揮のもと、妻も子どもも労働に従事していたわけです。
住まいと仕事場の区別はあいまいで、そこでは食事の用意や掃除など職務以外の作業が多くありました。その担い手としては、妻/女性が主でした。ただ、家業では住まいと職場が重なっていることが多く、家事という概念はそれほど明確に認識されていなかったと見られます。
女性のパートタイマーや非正規雇用は男性の2倍以上
18世紀のイギリスで始まった産業革命をきっかけに、各国で工業化が進み、こうした職住近接のライフスタイルが大きく様変わりしていきます。
特に、日本の場合、大正期ごろから会社や工場に勤めて報酬を得るという雇用労働が都市部を中心に増えていきます。ただ、夫婦が二人とも雇用労働に従事してしまうと、子どもの面倒を見る人がいなくなってしまうため、片方が家庭に残りました。たいがいそれは妻で、これが専業主婦の誕生につながるわけです。
日本で専業主婦の割合がピークに達した1970年代は、団塊世代の子育て期に当たります。地方から上京して都市部で暮らす夫は、適齢期に故郷でお見合い結婚をして妻を呼び寄せ、ニュータウンと呼ばれる団地に新居を構える。これが当時のトレンドでした。
しかし、その後のバブル崩壊で男性の所得が伸び悩み、家計を支えるために女性がパート労働に参加していく流れができていきます。この延長線上に今があります。フルタイムで働く女性が増えてはいるものの、パートタイマーなど非正規雇用はまだ男性の2倍以上という多さです。基本的にはまだ男性がメインで稼いで、女性がサブというところで止まっているということです。
特に子育て世代、30代前後の女性ではパートタイマーなど短時間労働者が一番多く、次が専業主婦で、正規雇用は実は少数派です。フルタイムの共働きは都市部では珍しくありませんが、全国的にはかなり少ないのが現状です。
男性並み平等の働き方には限界がある
1986年に男女雇用機会均等法が制定されたにも関わらず、なぜ女性の正規雇用が少ないかといえば、いわゆる大企業型の働き方が温存されているからです。
大企業型の働き方を象徴するのが、ワーカーが受け入れを余儀なくされる3つの無限定性でしょう。すなわち企業の裁量で配属先が決まる「職務内容の無限定性」、社員に転勤を命令できる「勤務地の無限定性」、時間外労働の日常化に見られるような「労働時間の無限定性」です。女性がこのハードな労働環境に入るのは、特に子育て期の場合、厳しいと言わざるを得ません。
1990年代に国は育児休業やエンゼルプラン* といった形で、働きながら子育てをする環境の拡充に乗り出しました。しかし、要は女性に男性と同じ働き方を求めつつ、育児期だけは助けましょうという施策だったため、うまく機能しませんでした。女性は育児期だけサポートしてもらっても、後がきついので結局仕事を辞めざるを得ないのです。
実際、2000年前後の調査では総合職女性が大量に離職していた実態が明らかになりました。男性並み平等の働き方には限界があるということです。
フルタイムの共働きが多いアメリカと北欧でも内情は違う
アメリカや北欧はフルタイムの共働きが多いです。これは男性的な働き方が日本ほどきつくなくて、女性も対等に働ける環境が整っていたことが理由に挙げられます。とはいえ、アメリカと北欧の内情は違っています。
アメリカは「自由主義路線」で、法律や施策など公的なバックアップはそれほどありません。しかし労働の規制緩和や公共企業の民営化が進んでいるため、男性と同じ土俵で競争させられるという厳しい状況ながらも、女性が労働市場に参加しやすいんですね。なので、アメリカでは夫婦で頑張ってフルタイムで働いて、子育ては民間の保育サービスを利用するというパターンが多いです。
北欧諸国がとっているのは「社会民主主義路線」です。失業者に公的給付を行うほか、政府が主導して職業訓練の機会を提供し、失業者に再雇用の道筋をつけるという積極的労働市場政策が特徴です。
特にこの政策を長く続けているのがスウェーデンで、福祉分野などで多くの女性を公的に雇用しています。公務員なので給料はそれほど高くないけれども、それでも日本のパートタイマーより安定しているし、育児休業や保育の制度もしっかりしていて、仕事と子育ての両立はしやすいといえるでしょう。
女性が子育てや介護を担う国は出生率が低い
アメリカの自由主義路線や北欧の社会民主主義路線と並べると、日本は「保守主義路線」、もしくは女性の労働人口が増えないという意味で「労働力縮小路線」ともいえます。
海外で似たような路線の国というとイタリアとドイツです。すなわち、女性が子育てや介護を担いがちな国ということ。日本とドイツとイタリアが先進国の中では極端に出生率が低いのですが、それは女性にいろいろ求め過ぎていることの裏返しの事象といえるでしょう。
自由主義路線も社会民主主義路線も、根本の発想は違っていても、女性が働きやすい素地があることは確かです。そもそも海外では転勤が基本的にないので、同じところで働き続けることができます。評価の仕方にしても、職務内容とそれに応じた賃金が決まっているジョブ型がメインなので転職がしやすい。転職しやすいということは、生活の変化に合わせて柔軟に働けるということです。
日本では転職するたびに賃金が下がりがちなので、出産・育児で離職した後に復職しようとしても、またゼロからのスタートになってしまう。正社員から専業主婦になった人が正規雇用に戻るには、高いハードルが課せられるわけです。職を転々とできて、なおかつ時給が一定の職業を日本で探すと、おおむね低賃金のパートやアルバイトということになります。そうすると共働きとしてはあまり戦力にならず、女性の経済力は上がっていきません。
(トップ写真:Standsome Worklifestyle on Unsplash)

筒井氏のブログ「社会学者の研究メモ」。
https://jtsutsui.hatenablog.com/

筒井氏。取材はオンラインで行った。
* 1991年、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(通称:育児介護休業法)が制定された。また、少子化対策として仕事と子育ての両立を支援する「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」(エンゼルプラン)を1994年に文部、厚生、労働、建設の4大臣の合意で策定。1999年に「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」(新エンゼルプラン)を大蔵、文部、厚生、労働、建設、自治の6大臣合意で策定した。
スウェーデンでは地方自治体が保育施策を担うが、待機児童が発生することは違法とされている。「保育の受け皿がないから働けないという人を誰一人として生み出さないと、法律で決めている。日本とは法律の整備からして状況が違います」(筒井氏)。

無限定性の是正や仕事と子育ての両立支援で
育児・介護ケアの家族負担を軽減
大まかにいいますと、育児・介護ケアの担い手について、自由主義路線では市場、社会民主主義路線では政府、保守主義路線では家族が重視される傾向にあります。
日本の場合、1970年代に当時の自民党が提起した政策方針である「日本型福祉社会」の考え方が根強く残っていることが、性別分業の背景にあると考えられます。この方針で強調されたのが、まさに「家族の大切さ」なんですね。福祉の担い手として重視されたのは、政府ではなく企業と家族であるとされました。
この日本型福祉社会の発想が今も引きずられているわけですが、現代では少子化対策や労働力の拡充が喫緊の課題であり、その観点に立つと、家族に過大な負担をかけるべきではないでしょう。無限定的な働き方を是正したり、仕事と子育ての両立を支援したりする施策を通じて、まずは家族へのしわ寄せを取り払っていく。そのうえで規制緩和や公的雇用といった他国の政策を参考にするのが有効だと思います。
家事の性別分業の背景にあるのは、夫婦双方の固定観念
家族の負担軽減や女性の働きにくさを考える上で見逃せないのが「家事」です。
日本人の家事労働時間は国際的に見ると長いです。そして、その担い手は女性/妻に偏っています。男性の家事の時間は10年間で1日6分ほどしか増えていません。**
先進国では家事代行サービスやお手伝いさんを雇うことが珍しくありませんが、日本ではトラブルを回避したいとか外の人を家に入れたくないといった意識が働いて、自分たちでこなそうとする。それも妻の負担につながっています。
ともあれ、家事労働におけるこの偏りがなぜ発生するのか。最大の要因は、夫婦双方が固定観念にとらわれているからだと思います。
父親が会社勤めで母親が専業主婦という家庭で育ったことで、そういう性別分業を当然のものと受け入れる人もいるでしょうし、あるいは身近な基準を参照して自分もそれにならおうとする人もいる。夫が男の友人や同僚から「俺は家事なんてしない」と聞いたら、「どうして周りはやっていないのに俺だけやるのか」と思うでしょうし、妻は妻でママ友同士のおしゃべりで「ダンナって家で何もしないよね」と聞けば、「どこの家もそんなものか」と思ってしまう。そういうことって珍しくないと思うんです。
人間はたいてい自分の都合のいいところを見ようとしますからね。特に男性は自分より家事をしていない男性を見つけて、その存在を自分が家事をしなくて済む免罪符にする傾向がある。家事を平等に分担する強力なロールモデルが出てくると状況は変わっていくかもしれませんが、今は相変わらず身近なぬるいモデルが基準になっていると感じます。
家事は仕事の延長線上で考えたほうがいい
家事の担い手が偏ることの背景にはもう1つ、スキル格差もあるでしょう。
家事はこまごました作業を同時並行で進めなければならず、その難しさや手間は過小評価されています。例えば普段調理をしない男性がたまに夕食を準備するとなると、スーパーでお肉を買ってきて焼くだけだったりする。冷蔵庫の食材を確認もせず、栄養バランスも家計も考えない。これは仕事に置き換えたら一部の作業を切り出して勝手に完了しただけで、会社だったら「仕事ができない人」だと思われますよね。
本当は会社でも内容を一言で言えないような下支えの作業はいくらでもあるのですが、総務課や庶務といったセクションが引き受けているわけです。だから組織が全体として回っていく。それと同じことで、家事は仕事の延長線上で考えたほうがいいのかもしれません。
家事をこなす女性が細かいことを同時進行でこなすことができるのは、社会的圧力の結果として訓練された結果でもあるでしょう。夫が思うように家事をしてくれないからといって、自分でやってしまいたくなる気持ちもわかるのですが、それでは夫はいつまでも戦力外のままです。
特に日本はクオリティの高い家事を要求するので、妻の側も夫の提供する家事レベルに慣れないといけない。「もう少しちゃんとやってよ」と文句を言うのではなく、「仕事ができる人だったらこうやるんじゃないかな」と、夫のプライドを刺激してみてはどうでしょう。夫の立場からすると家でも仕事をするようで嫌だと感じられるかもしれませんが、家の中にも面倒な仕事が山ほどあるという現実を認めないと、女性の負担は減らないと思います。
格差の連鎖を招きかねない「同類婚」の増加
もう1つ、家族をめぐる視点として重要なのが格差の問題です。
家事分担や職務慣行など、これまで説明してきたような女性に不利な要素が解消されて共働き社会が実現した場合、地位が同じような男女がカップルを形成する同類婚が進むと予想されます。
現にアメリカではそういう現象が見られます。経済力や学歴が同等で、宗教や人種・民族も同じといった具合で、ともに高所得者の男女からなるパワフル・カップルは増加傾向にあります。
同類婚が増加すれば、カップル間の階層格差は拡大するでしょう。もしかしたら階層が下のほうになると結婚が成立しにくくなるかもしれない。これもアメリカでは現実に起こっていることで、所得の不安定な人は結婚が難しい状況です。
さらに、カップルの格差からは家族の格差も生じるでしょうし、ひいては子どもにもその格差が受け継がれることが懸念されます。格差の連鎖を断つには、所得の高いところから低いところへ再分配して、社会保障や福祉を充実していくしか選択肢はないのかなと思います。特にコロナ禍で職を失い困窮する人が多くいる今、ある程度目配せしておかないと格差の固定化や深刻な社会的分断を招きかねません。
ただ、現状では再配分をもっと大々的にやるべしとする社会的合意は得られにくいでしょうし、そもそも配偶者を自由に選べることは基本的人権であって、第三者がとやかく言えることではありません。同類婚の問題は非常に難しく、複雑さをはらんでいます。結婚、家庭、仕事を包括的にとらえて、連帯に向けて社会を形成していくために、一人ひとりが当事者の意識をもって議論していくことが求められていると思います。
WEB限定コンテンツ
(2021.1.13 オンラインにて取材)
text: Yoshie Kaneko
(写真:Atharva Tulsi on Unsplash)
** 1日の家事関連時間を2006年と2016年で比較すると、女性は3.35時間→3.28時間、男性は0.38時間→0.44時間という結果だった。(平成28年社会生活基本調査(総務省統計局))

筒井氏の著書『仕事と家族――日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか』(中公新書)。仕事と家族をめぐる日本の諸問題を、歴史的かつ国際的な視点を通じてあぶり出している。

筒井淳也(つつい・じゅんや)
1970年福岡県生まれ。一橋大学社会学部卒。同大学大学院社会学研究科博士課程後期課程満期退学。博士(社会学)。現在、立命館大学産業社会学部教授。専門は家族社会学、計量社会学。著書に、『制度と再帰性の社会学』(ハーベスト社)、『親密性の社会学』(世界思想社)、『仕事と家族』(中公新書)、『結婚と家族のこれから』(光文社新書)、『社会を知るためには』(ちくまプリマー新書)など。(写真提供:筒井氏)


![働くしくみと空間をつくるマガジン[ワークサイト]](/images/common/ttl-catch_copy-002.png)