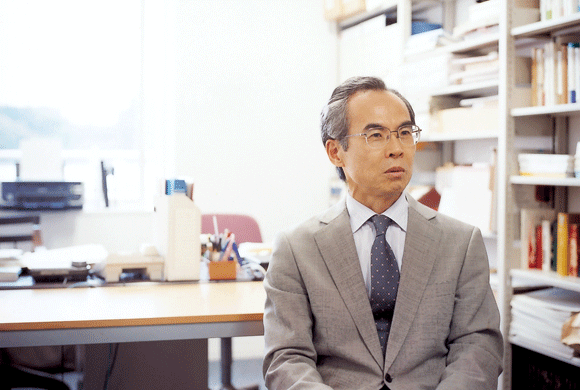Innovator
Jan. 20, 2014

「問い」そのものを見直すことから
デザインイノベーションが始まる
見えない「関係性」をデザインするプロセスとは
[太刀川英輔]NOSIGNER代表
何らかの問いに解答を出す、というのは1つのデザインのあり方です。ただ、その問いがシンプルな要素で構成されているほど、デザインはレバレッジが効いて、多くの課題を一気に解決でき、うまく機能するんです。ですから、問いが与えられた時点で、その問いをシンプルに捉え直します。
まず、そもそもなぜその問いになったのか、クライアントに必ず確認します。なぜかというと、大体は問いそのものが間違っていて、より本質的でシンプルな問いを発見し直す必要があるからです。
ほぼ全てのプロジェクトは、リアルな困り事から始まります。「売上げを増やしたい、だからこういうプロジェクトを立ち上げたからデザインをやってくれ」というわけです。でも僕はそこで「そもそもなんで売上げを増やしたいの?」というところに1回戻るんです。例えば、それは会社のためなのか、社会のためなのか。社会のためというなら、売上げを伸ばすことがどう社会に作用するのか。こういう禅問答みたいなことをして、問いを大きく、シンプル、クリアなものにしていきます。
例えば、モジラジャパンの新オフィスをデザインしたプロジェクトは、時間が限られているなかで内装のデザインをお願いできないか、という依頼でした。でも僕は、「やってみたいことがある」といって、その問いを完全に設計し直すことにしました。
モジラは世界最大規模のオープンソースコミュニティです。だったらオフィスをデザインするにも、その時間的・コスト的な課題も全部ひっくるめてオープンソースの手法で解決しようと提案しました。それができたら単に「オフィスを新しくする」という概念を超えられますよね。
そこで僕たちは、オフィスの空間構成をすべてオープンソース化することにしました。これはモジラのブランディング上すごく強力なメッセージになりますし、世界の人がワクワクするような魅力あるプロジェクトになると考えたんです。
対象そのものではなく、対象をどう理解していたのか
僕たちのデザインのプロセスは、リサーチ→コンセプト→デザインと進みます。最初は、漠然と対象をリサーチして、理解するフェーズです。例えば今、東京フィルハーモニー交響楽団のブランディングを行っていますが、クラシックを知らない僕がオーケストラのブランディングをするというとき、2つの視点からリサーチを行います。
まずは、文脈や背景、文化の下地の部分を俯瞰できるよう「周辺状況」についての情報を集めます。それから、素人である自分自身がどうクラシックを理解していたかその「理解のプロセス」の部分を確認します。例えば、クラシックコンサートのチケットは高いと思い込んでいたのに、案外安いチケットもあるのだとか。
この時点で、なんでこんな認識だったんだろう、本来ならどういう認識であるべきなんだろう、みたいなことも考えていくわけですね。すると、本来の期待に叶うコンセプトを生みだす感覚が養われます。この感覚は大きな問いを解くためのデザイン検証の下地になります。
 「NOSIGNER」は平面、立体、空間など既存のジャンルにとらわれず活動するデザインファームだ。
「NOSIGNER」は平面、立体、空間など既存のジャンルにとらわれず活動するデザインファームだ。
http://nosigner.com/
 Mozilla Japanの新オフィスであるMozilla Factory Spaceの様子。空間構成アイデアは「オープンソースファーニチャー」として、すべての図面・制作手順を公開しており、誰でも機能的なオフィスを構築することができる。
Mozilla Japanの新オフィスであるMozilla Factory Spaceの様子。空間構成アイデアは「オープンソースファーニチャー」として、すべての図面・制作手順を公開しており、誰でも機能的なオフィスを構築することができる。

純度の高い「大きな問い」を
「シンプルなデザイン」で突き抜ける
そのうちに、あるとき状況がなんとなく理解できるようになります。そこからは、コンセプトを固める仮説検証の作業です。仮のコンセプトを出す、捨てる、また出す、捨てる。その繰り返しです。
何を基準に取捨選択するかというと、やはりここでもコンセプトを理解するスピードや理解するときのプロセスを見ています。
ただ、それは一度形にしてみないと判断できない部分も多々あります。これはいいと思ったものでもいざ形にしてみると何か違う、というものも少なくありません。なので、プロトタイプを作り、クライアントとも話をしながら、それを見て捨てる、また作って、見て捨てる、といったフェーズがあります。
そして、いざコンセプトが決まったら、それをデザインの形に固める作業があります。この作業はきわめて職人的で、いわゆるデザイナーとしてのスキルが問われる部分です。
こうした一連の流れは、気体→液体→固体といった状態変化に近いと思っています。気体のような漠としたものをたくさん集めて、そこに圧力みたいなものをかけると流動的ではあるがコンセプトが見えてきて、ある段階でそれをデザインとして固体化するイメージです。
突き抜けるためには「ゴールイメージ」ではなく「OBライン」を共有する
こうしたプロセスは、カウンターパートであるクライアントと一緒に進めていくのがベストです。特に期待するのは、クライアント自身が自分の課題ややりたいことをクリアに持っていること。「こういうのがいい」とはっきりしている少人数のチームと始めるのが、一番うまくいくパターンです。実際はその周辺にいる別の立場の人達にも話を聞きに行きます。
コンセプトを仮説検証で回していくフェーズにたくさんの人数が必要かというと、僕はそんなことはないと思っています。要するにスモールチームで、こちらのチームが2、3人、クライアント側にも2、3人いればいい。また、そのなかにバンバン意志を示してくれる人がいると、ぐっとやりやすくなります。仮説検証のキャッチボールが早くなりますから。そのキャッチボールが早いほど、問題の全体像を正しく把握するのも早くなります。
逆に、意志がふわっとしている人、プロジェクトの成功や、その先にある大きな目的のために動いていない人がいると、一連のプロセスが立ち遅れてしまいます。
またこうした集合知的なデザインをするときに大切なのは、”OBライン”の設定です。「これはダメ」「これは考える必要がない」というOBラインをリサーチを通じてシェアしていると、アイデアが拡散していくのを防ぐことができますし、その制約そのものがデザインのヒントになります。こうした感覚を揃えるということは実はあんまりデザイン思考のプロセスのなかで重要視されていないけど、ものすごく大事なことだと思うし、それをやらない限り、集合知のデザインはできない。
技術的な制約も代表的なOBラインですね。例えばコップのデザインを考えるにも「液体をテーブルの上から効率的に運ぶ道具」「手の平のサイズに納まるもの」といった制約条件がなければ、いつまでもアイデアが集約しません。
良い問いとOBラインがわかれば、あとはできる限りシンプルに思いっきり遠くまで飛ばす方法を探すだけです。
僕たちのような関係性全体をデザインしようとする人間に求められる資質は「想定する力」だと思っています。いろんな人のいろんな立場になりかわってものを考える力。僕は「イタコ力(りょく)」と言ってるんです。「このお客さんはこのへんが大変だろうな」「営業サイドはこのあたりを悩んでいるな」とか。こうした力が、先週の記事でも述べた「観の目」につながる。目の前のデザインを超えて、その先にある人や社会との関係性を考える上では必要になるんです。
WEB限定コンテンツ
(2013.11.29 横浜市関内の同社オフィスにて取材)
 現在、スタッフは5名。プロダクトデザイナーだけでなく、元雑誌編集者やグラフィックデザイナーなど、異分野のプロフェッショナルが集まった専門家集団だ。
現在、スタッフは5名。プロダクトデザイナーだけでなく、元雑誌編集者やグラフィックデザイナーなど、異分野のプロフェッショナルが集まった専門家集団だ。

 国産と天然にこだわったスキンケアブランドwarew<和流>のブランディングや、0〜6歳の子どもに向け、日本の伝統産業品を届けるaeruのデザインなど幅広く手掛けている。
国産と天然にこだわったスキンケアブランドwarew<和流>のブランディングや、0〜6歳の子どもに向け、日本の伝統産業品を届けるaeruのデザインなど幅広く手掛けている。

太刀川英輔(たちかわ・えいすけ)
1981年生まれ。法政大学工学部卒業後、慶應義塾大学大学院理工学研究科へ。在学中の2006年にNOSIGNERを立ち上げ、プロダクトからグラフィック、空間デザインまで、ジャンルを問わずデザインを手掛ける。SDA AWARD サインデザイン最優秀賞、DSA AWARD 空間デザイン優秀賞をはじめDesign for Asia Awardなど、国内外の様々なアワードを受賞。


![働くしくみと空間をつくるマガジン[ワークサイト]](/images/common/ttl-catch_copy-002.png)